お知らせ(事件報告・提言)
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対する意見書
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対するパブリックコメント募集に対し、被害者救済の観点から、意見書を提出しました。
意 見 書
法務省法制審議会民法(債権関係)部会 御中2013(平成25)年6月17日〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩1-7-9
西新小岩ハイツ506 福地・野田法律事務所内
TEL 03-5698-8544 FAX 03-5698-7512
医療問題弁護団 代表 鈴 木 利 廣
記
意見書の趣旨1 消滅時効の時効期間について(中間試案第7「2」、同「5」)
少なくとも生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、現行民法167条1項における10年の時効期間を維持すべきである。2 法定利率及び中間利息控除について(中間試案第8「4」)
(1)中間利息控除率を年5%とする規定(【第8、4(3)】の規定)の新設に反対する。
(2)「損害賠償額の算定に当たって中間利息控除を行う場合の控除率は、損害賠償の発生原因が生じた時の法定利率による。」との規定を新設すべきである。
意見の理由1 消滅時効の時効期間について
中間試案第7「2」では、債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点について、「【甲案】『権利を行使することができる時』(民法第166条第1項)という起算点を維持した上で、10年間(同法第167条第1項)という時効期間を5年間に改めるものとする。
【乙案】『権利を行使することができる時』(民法第166条第1項)という起算点から10年間(同法第167条第1項)という時効期間を維持した上で、『債権者が債権発生の原因及び債務者を知った時(債権者が権利を行使することができる時より前に債権発生の原因及び債務者を知っていたときは、権利を行使することができる時)』という起算点から[3年間/4年間/5年間]という時効期間を新たに設け、いずれかの時効期間が満了した時に消滅時効が完成するものとする。」との提案がなされている。
そもそも消滅時効制度は、主に義務者側の都合(永続した事実状態の保護、権利の上に眠る者は保護しない、証明困難の救済)によって義務者を救済する制度であり、「不道徳な制度」と言われることもある。
生命・身体を侵害された事例で、容易に時効消滅が認められれば、義務者(加害者)は責を免れる一方で、権利者(被害者)は被害救済を受けられないという不当な結果を招来することになる。
生命身体被害の侵害に対する損害賠償請求権について消滅時効の適用を拡大する方向性での民法改正は、生命身体という重要な保護法益の軽視であると言わざるを得ない。
生命身体の保護・被害救済の観点からすれば、消滅時効の適用は安易に拡大されるべきではなく、むしろできる限り適用を限定すべきである。
また、①医療事件等人身被害を引き起こす事件では、(a)被害者(患者)が事故による障害を、あるいは、遺族が被害者(患者)の死亡を、受容できない、(b)重度の後遺障害が発生した場合、家族が被害者(患者)の全生活面にわたり看護・介護等に当たらなければならない、(c)事故があった医療機関で現に治療等を継続して受けている場合、当該医療機関に対する責任追及を控えてしまう等様々な事情によって、心理的にも経済的にも時間的・労力的にも、法的責任追及をするところまで到達するのに長い時間を要する。
さらに、②医療事件においては、患者ないし遺族は通常医学的な知識を有しておらず、債務不履行を基礎付ける事実(診療経過事実)については医療機関の支配下にあるカルテが最重要かつ有力な証拠であるところ、医学知識及び証拠が偏在していることなどから、患者ないし遺族が、患者が受けた医療に問題があったことを認識することにすら困難が伴い、責任追及に及ぶまでに相当の時間を要する。
そして、実際の訴訟において、債務不履行に基づく損害賠償請求が、消滅時効を理由として棄却された例が認められる(大阪地判昭和63年7月15日、京都地判平成14年5月8日、東京地判平成20年11月27日など)。
かかる医療事件等人身被害を引き起こす事件の特殊性にも鑑みると、消滅時効の期間を短縮し、消滅時効の適用を拡大することは、患者ないし遺族が被害救済を受ける機会を不当に奪う結果を招来するため、到底是認できない。
この点、中間試案第7「5」では、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について、「生命・身体[又はこれらに類するもの]の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、前記2における債権の消滅時効における原則的な時効期間に応じて、それよりも長期の時効期間を設けるものとする。」との提案がなされているところである。
当弁護団としては、上記第7「5」の提案がなされた趣旨を支持した上で、少なくとも生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、現行民法167条1項における10年の時効期間を堅持することを要望する。2 法定利率及び中間利息控除について
(1)中間利息控除の意義
逸失利益や将来の介護費用等将来の損害の賠償については、将来損害を現在の価額に換算して、先に損害賠償金を受け取る処理がおこなわれている。将来損害を現在価額に換算するために運用利益を控除する。
運用利益を控除するには、平均的な市場金利で中間利息を控除することが必要となる。
(2)民事法定利率の根拠
民法は、金銭消費貸借において、貸主・借主が利率を定めなかった場合の利率(民事法定利率)を定めている。
現行民法は、年5%の民事法定利率を定めている(民法404条)。この年5%という利率は、民法制定当時の平均的な市場金利を反映したものである。
民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率、我が国の一般的な貸付金利を踏まえ、民法制定当時、金銭は通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。
(3)中間利息控除率は民事法定利率に拠るべきこと
現行民法に中間利息控除率を定める条項はないが、最高裁(三小)平成17年6月14日判決(金谷利廣、濱田邦夫、上田豊三、藤田宙靖)は、損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならない、と解釈している。
民事法定利率は、現民法の建前では平均的な市場金利であるから、法体系上、平均的な市場金利であるべき中間利息控除率は民事法定利率によるべきとなるからで、またそのことに一応の合理性があるからである。※註参照
(4)年5%の利率の問題
年5%の利率は、民法制定当時と異なり、現在では、平均的な市場金利から乖離し、著しく高率である。そのため、過大な中間利息控除によって、一般市民には絶対に運用不可能な利率で中間控除がなされ、将来損害の賠償金が著しく目減りするという不合理な事態が生じている。
この不合理な事態は、中間利息控除率イコール民事法定利率であるからではなく、民事法定利率が平均的な市場金利から乖離していることに起因している。
(5)「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について
(5)-1 民事法定利率について
ところで、民事法定利率が平均的な市場金利からかけ離れている現状を正すために、民事法定利率を年3%に引き下げ、さらに一定期間の平均的な市場利率と連動するものにしよう、という民法(債権関係)改正が提案された。これは、適切な改正であると評価できる。
(5)-2 中間利息控除について
ただ同時に、中間試案は「損害賠償額の算定に当たって中間利息控除を行う場合には、それに用いる割合は、年[5パーセント]とするものとする」として、中間利息控除率だけは現状通り年5%を維持しようとしている。この点は問題である。
中間利息控除率は、上述のとおり運用利益を控除(中間利息を複利計算で控除)するものであるから、法体系上平均的な市場金利を反映するはずの民事法定利率と同率であるべきである(上記最高裁の考え方)。
民事法定利率について、平均的な市場金利に近づけるための改正が行われようとしているのに、中間利息控除率だけを年5%と維持とするのは、法体系上不整合である。
中間試案で民事法定利率を引き下げるのは、5%という民事法定利率が現在及び将来みこまれる実勢金利から著しく乖離しているという立法事実が確認されていることに基づく。
この立法事実が確認され民事法定利率が引き下げられる以上、中間利息控除の利率についても民事法定利率と足並みをそろえて引き下げるべきである。
また、実際上も著しい目減りが生じている現状を放置することになり著しく不合理である。
5%の利率(複利)で中間利息を控除されるため、医療過誤の被害者は、将来分の損害について著しく目減りした金額しか受け取れない。
医療過誤の被害者が中間利息控除を受ける主な費目は、逸失利益と将来の介護費用である。
多くの被害者は、日々の介護や生活に追われ、獲得した損害賠償金をより効率的に運用する時間的精神的余裕もないのが実情である。
これは、交通事故、労災事故や犯罪被害など人身被害により損害賠償金を取得する被害者に共通するところである。
少なくとも、被害者が我が国のごく一般的な市民が資産を運用した場合に得られる以上の運用益を得られると想定する根拠はどこにもない。
被害者がこれらを獲得することを想定して法設計することは、著しく不正義である。
したがって、民事法定利率を引き下げ一定期間の平均的な市場利率と連動するものに改める以上は、中間利息控除率も同様とすべきである。
なお、現民法は、中間利息控除率を定める法文をおいていないが、今後の法定利率の改正に対応するために、この機会に、中間利息控除率について(一定期間の平均的な市場金利を反映するはずの)民事法定利率と同率とする旨の規定をおくべきと思料する。※註 最高裁(三小)平成17年6月14日判決は、民事法定利率は金銭の通常の利用方法によって生じる利息に鑑みて定められるものであるとしたうえで、「現行法は、将来の請求権を現在価額に換算するに際し、法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には、法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している。
例えば、民事執行法88条2項、破産法99条1項2号(中略)、民事再生法87条1項1号、2号、会社更生法136条1項1号、2号等は、いずれも将来の請求権を法定利率による中間利息の控除によって現在価額に換算することを規定している。
損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても、法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから、民法は、民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。
このように考えることによって、事案ごとに、また、裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ、被害者相互間の公平の確保、損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。
上記の諸点に照らすと、【要旨】損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならないというべきである。」と判示した。
以 上

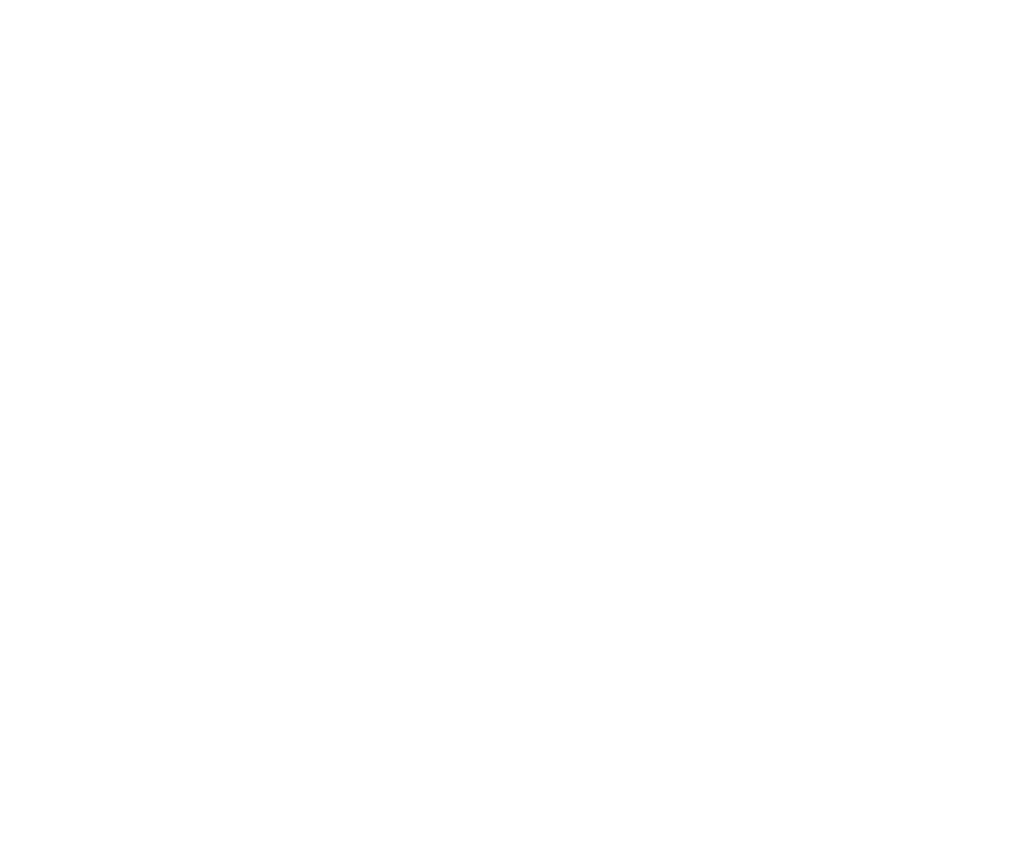 公式ツイッター
公式ツイッター