団員リレーエッセイ弁護士の声
医療事故と内部告発
弁護士 安 東 宏 三
つい先日、私も患者側弁護団の一員として関与したある医療過誤事件で和解が成立した。いわゆる東京医大事件である。
2002年末から2004年1月までの間に、東京医大で、同じ医師の弁置換手術を受けた心臓弁膜症の患者4名が次々に死亡するという事件があった。一般に、弁置換術は心臓外科分野では技術的にほぼ確立した手術とされており、死亡率も高くない。それが同じ医師の関与の下で4件続けて死亡というのは、異例中の異例の事態である。
実は、この事件が明るみに出たきっかけは、内部告発だった。3例の死亡が続いた時点で、東京医大内部の人間から匿名の告発が新聞社になされたのである。しかし、新聞社が告発者にアクセス出来ないでいるうちに、4例目の死亡が出てしまう。告発者は再度新聞社に連絡してきた。「まさか、まだ手術を続けさせるなんて思ってもみなかったんです。なぜみんな平気なんでしょう。どうして黙っているんだろう。……」
新聞社は、必死で告発者とのコンタクトを成功させ、相談を受けた私ども医療問題弁護団は、秘密裡に担当チームを作り対策を練った。情報を収集すると、大学の医局の一部からもこの医師が手術を担当することには疑問の声が出ていたが、絶対の決定権をもつ主任教授は彼を重用し、手術を続けさせようとしていた。大学内部の歯止めは既に機能していない。このままではいずれ「5例目」が出てしまう。
そこで私どもが選んだ方法は、裁判所による証拠保全という公的な手続を開始すると同時に、問題を紙面で大々的に叩く、ということであった。敢えて大学の外から容易ならざる事態を作り出すことによって、「5例目」をなんとか止めようとしたのである。
その後、証拠保全、事故調査委員会による調査等を経て、大学側は最終的には責任を認めるに至り、東京医大の心臓血管外科の体制は一新された。あの内部告発がなければ、およそ考えられない解決ではあった。(もし詳しい経緯に興味をおもちの方があれば、読売新聞社会部編「大学病院でなぜ心臓は止まったのか」(中公新書ラクレ、2006年)をご覧下さい。)この事件を通じて、私どもは、内部告発がわれわれの社会のもつ「最後の安全弁」であることを、改めて痛感したのである。
ところが、つい最近、恐ろしい判決がでた。
日本医大で顎の骨折の手術中に、患者の脳に誤ってキルシュナーワイヤーが刺入したと遺族(患者は死亡)に告白し謝罪した医師を、こともあろうに大学当局が名誉毀損で訴え、しかもその大学側の請求が認容されてしまったのである。
名誉毀損的な言論も、公益目的等でなされた場合は、その摘示した事実が真実であるか、そうでなくとも、真実と考える相当の根拠があった場合は、免責される。本件でワイヤーが脳内に刺入したかどうかについては、証拠となる画像の読影等を巡って現在も本体の民事訴訟で争われている。 しかし、(担当事件ではないので側聞する限りではあるが、)少なくともこの画像を「刺さっている」と読影する大学教授クラスの専門医が多数おり、どんなに控えめに見ても、「刺さったと考える相当の根拠がある」という限度では免責が認められるべき事案であったと思われる。(実際、1審の東京地裁はこれを認めた。)
しかし、控訴審の東京高裁はこれを否定して医師に損害賠償を命じ、最高裁もこれを追認して上告を棄却してしまったのである。自らの良心から遺族に告白し謝罪したこの医師は、大学に対して、利息を含めて約700万円の支払いを余儀なくされたという。
このようなことがまかり通るのであれば、大学の意向に反して内部告発をしようとする者など誰もいなくなり、われわれの社会は最後の安全弁を失ってしまうだろう。もう、次の「5例目」は止められないかもしれない。恐ろしい、本当に容易ならざる事態というほかはない。

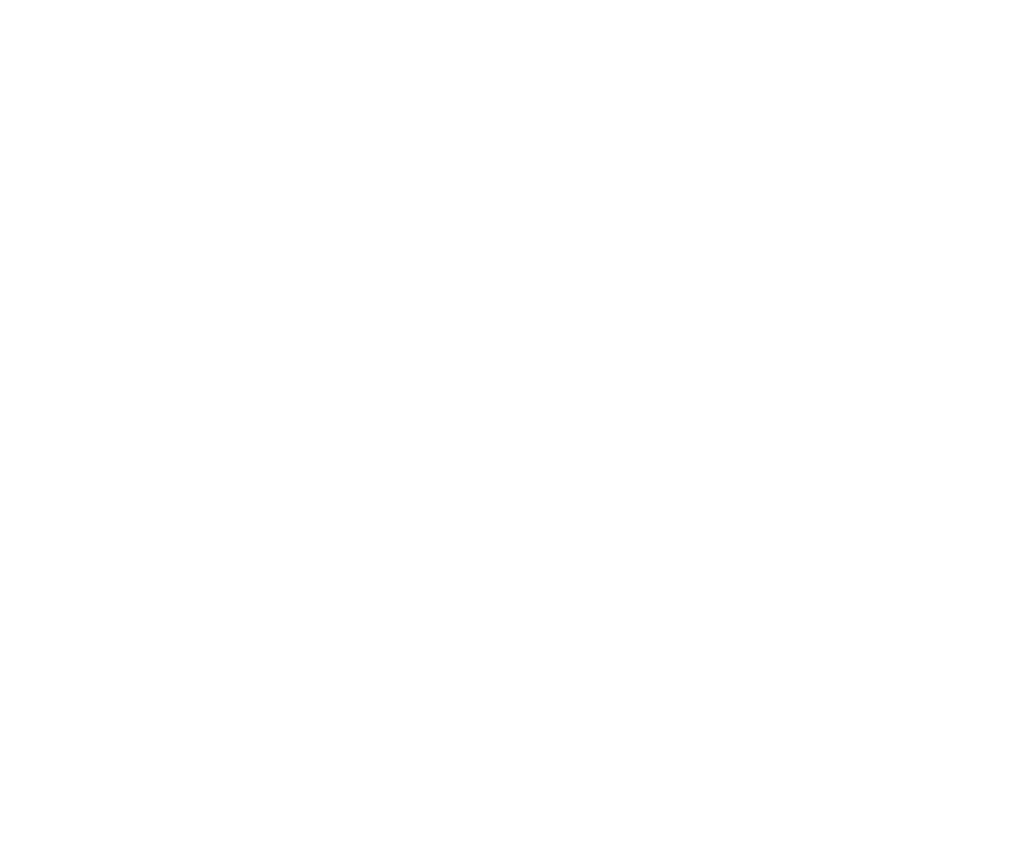 公式 X
公式 X