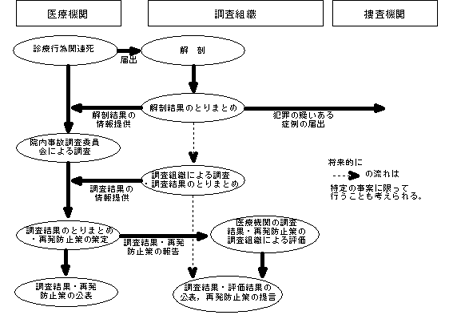当弁護団は、東京を中心とする200名余の弁護士を団員に擁し、医療事故被害者の救済、医療事故の再発防止のための諸活動等を行い、それを通じて、患者の権利を確立し、かつ、安全で良質な医療を実現することを目的とする団体です。
「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性について」に関して、下記のとおり、意見を提出いたします。
平成19年4月20日
医療問題弁護団
代表 弁護士 鈴 木 利 廣
(事務局)
東京都葛飾区西新小岩1-7-9西新小岩ハイツ506
福地・野田法律事務所内
電 話 03(5698)8544
FAX 03(5698)7512
ホームページ:http://www.iryo-bengo.com/
※ 本意見書に関する連絡は下記へお願いいたします。
東京都練馬区北町2-29-13 森ビル2階
きのした法律事務所 弁護士 木下正一郎
電 話 03(5921)2766
FAX 03(5921)2765
1.意見提出点
項目番号 1,2(1)②,3(1)及び 4(2)⑥
内容 (a)策定の背景について
(b)診療行為関連死の届出制度と異状死届出との関係について
(c)調査組織と院内事故調査委員会との関係について
2.意見
(a)について
今般の診療行為関連死の死因究明制度化は、医療事故防止のための必要不可欠な制度である。すみやかなる政策決定・実施が求められている。
(b)について
医療事故防止対策については、悪質な医療過誤犯罪を摘発するためのシステムと事故原因を究明して再発防止や被害救済という目的・理念に資するためのシステムの双方が必要である。
犯罪摘発システムについては、近年異状死届出義務が重要な捜査の端緒とされている一方、事故原因究明のシステムはいまだ存在しない。
今般、事故原因究明システムを設計するにあたっては、航空鉄道事故調査委員会設置法に基づく調査委員会が示唆的である。
事故報告は、航空機・鉄道の関係者から国交省に報告され、調査委員会の調査が開始される。刑事捜査との関係については、国交省と警察庁との間で「覚書」「実施細目」が合意され、刑事捜査と事故調査の調整がなされている。
ところで、現行法上の事故調査のあり様については、警察捜査を中心とする交通事故型と、警察と事故調査委員会の調整の下で行われている航空・鉄道事故型に分かれている。
医療事故調査については、医療の特殊性を踏まえ、上記目的・理念に沿って事故調査委員会を中心とする第3類型の創設をめざして、新たな整理を行う必要がある。
犯罪捜査より再発防止のための事故調査を優先させて、医療事故死の届出先を調査組織に一元化し、犯罪の疑いあるものについてのみ例外的に調査組織から捜査機関に届出させることが望ましいと考える。
そのためには、異状死届出義務の例外規定を含めた「診療行為関連死死因究明委員会設置法」(仮称)が必要と考える。
(c)について
診療行為関連死を含む重大な医療事故が発生した場合、原因を究明し再発防止を図るためには、医療機関の現場の努力とその英知を結集すること、すなわち院内事故調査委員会を設置して原因究明のための調査、再発防止策策定を行うことが必要である。
多数の医療事故の一部でしか原因究明の調査が行われていない現状では、院内事故調査委員会を設置して調査することを、法的に義務づけることが必要と考える。
なお、小規模医療機関においては、地区医師会等に委託し、地区医師会等が医療事故調査委員会を設置して事故調査を実施することも一案である。
この場合、当該事故調査を小規模医療機関の院内事故調査と位置づけることになろう。
院内事故調査委員会には、発生した医療事故ないし起因する医療行為等の分野の医療の専門家を、外部の者から任命することが重要である。
以上の院内事故調査委員会と調査組織の関係については、次のように設計すべきと考える(本意見書末尾の図参照)。
まず、診療行為関連死が発生した場合、医療機関は調査組織に届出をするとともに、院内事故調査委員会を設置し調査に着手する。
調査組織は、全例につき解剖(行政解剖)を実施し、解剖結果をとりまとめて医療機関に情報提供し、調査組織も調査権限をもって調査にあたる。
医療機関は、解剖結果や院内事故調査委員会の調査を踏まえ、調査結果をとりまとめ再発防止策を策定し、調査組織に報告するとともに、原則として公表する。
調査組織は、その院内事故調査結果を検討して評価し、自らの調査結果とともに評価結果を公表して、さらに再発防止策を提言する。
このようにして、医療事故の再発防止策を一般に知らしめるとともに、医療機関の院内事故調査体制の強化を図っていくことが重要である。
将来的に、院内事故調査体制が整備されてくれば、一定の医療機関での診療行為関連死については、調査組織は独自の調査は行わず、当該医療機関での院内事故調査の結果を事後評価するに留めることもありうると考える。
これに対し、医療機関に院内事故調査体制が整備されていない場合や、その他、被害が広範囲に及んでいる事案(院内感染事故等)、医療機関の院内事故調査に委ねると調査の公正性を損なうことが明白な事案、遺族と医療機関との信頼関係が崩壊し遺族が調査組織による調査を望む場合等には、調査組織が調査を実施するとともに、医療機関の行った院内事故調査結果を評価し、それらの結果を公表するという運用を維持する必要があろう。
なお、広く医療機関に院内事故調査体制を普及させるために、医療機関が適切に院内事故調査を実施した場合、これに要した費用を補填する等の手当も検討することが重要である。
図 診療行為関連死の死因究明等の流れ以上

 公式 X
公式 X