団員リレーエッセイ弁護士の声
母を看取って
弁護士 石 井 麦 生
昨年12月、母が76歳で亡くなった。夕食の準備中に気分が悪くなり、そのまま意識を喪い、それからたった3日後に息を引き取った。私が駆けつけたときには、既に意識はなく、結局、母と会話を交わすことはできなかった。
原因は、脳幹部の出血。担当医の一言目は、「出血の部位が悪い。助からない」であった。
わずか3日間だったが、入院先の病院に通い、医療の現実に触れ、いくつか考えさせられるところがあった。
一つ目。
母が倒れた日の夜9時に私は病院に着いた。担当医が私たち家族に求めたのは、「今日中に(つまり、3時間以内に)延命治療を受けるかどうかを決めてほしい」であった。担当医の言葉の端々に「延命治療なんて意味がありませんよ」というニュアンスが見え隠れする。私は父と話し合って、「延命治療を受けない」という選択をした。理由は簡単である。母が生前から「無駄な延命は嫌だ」と言っていたからである。しかし、この生前の言葉がなかったら、と思うと、医師は家族にずいぶんと厳しい回答を迫るのだなと感じた。
二つ目。
担当医は、「病状を説明します」と切り出し、大きな声で「ダメだ。意識は戻らない。助からない」を繰り返した。そこには、母・妻を突然喪うことになりかねない家族への配慮が微塵も感じられなかった。「説明する義務があるから、説明している」という姿勢だった。延々と続く担当医の説明は、ただただ不快であった。身なりがきちんとしていないことにすら、腹がたった。
ところが、その後、この担当医に感謝することになる。
担当医は、母を個室に運び込む際、こう言ったのである。
「お母さんは、今、努力性の呼吸をしています。傍で見ていると苦しそうですが、意識がないので、本人は苦しくはありません。大丈夫です」と。
確かに、意識のない母は、胸を大きく上下させて、「スーハー、スーハー」と音をたてて呼吸している。とても苦しそうだ。病室内の音は母の苦しそうな呼吸だけ。そんな母を前にして何もできない自分が情けなく、担当医の「本人は苦しくありません」という言葉だけが頼りであった。本当に本人が苦しくないのかどうかはわからないが、担当医の言葉は家族にとって救いであった。
三つ目。
看護師の対応如何で、家族は時に傷つき、時に癒されることを知った。
深夜1時頃、2人の看護師さんが病室を訪れ、まず痰の吸引を行った。鼻からチューブを入れると、母の体がビクッと動く。辛そうに見える。その後、「体位を交換します。汗をかいていて着替えが必要なので、病室の外で待っていてください」と言われ、私は病室から出た。ドアの外で待っていると、中から看護師さん達の話し声が聞こえる。内容は聞き取れない。そして、突然、笑い声が・・・。職場の同僚同士のたわいもない会話だろう。母は意識を喪っているので、聞こえはしない。でも・・・。ただただ涙があふれた。
3時を回ったところで、別の看護師さんがやってきた。痰の吸引のためである。看護師さんは、私の顔を見て、「息子さんですか。大変ですね」と声をかけてくれた。そして、この看護師さんは、意識のない母にも声をかけた。「○(母の名前)さん、痰の吸引をしますね。ちょっと辛いですけど、ごめんなさいね」と。有難かった。心の中で「母さん、辛いけど、頑張って」と言うことができた。
良い医療って何だろう。
もちろん、質の高い医療、安全な医療でなければならないのは当然。
そこから先のプラスアルファ。
それを求めるのは贅沢なことなのだろうか。

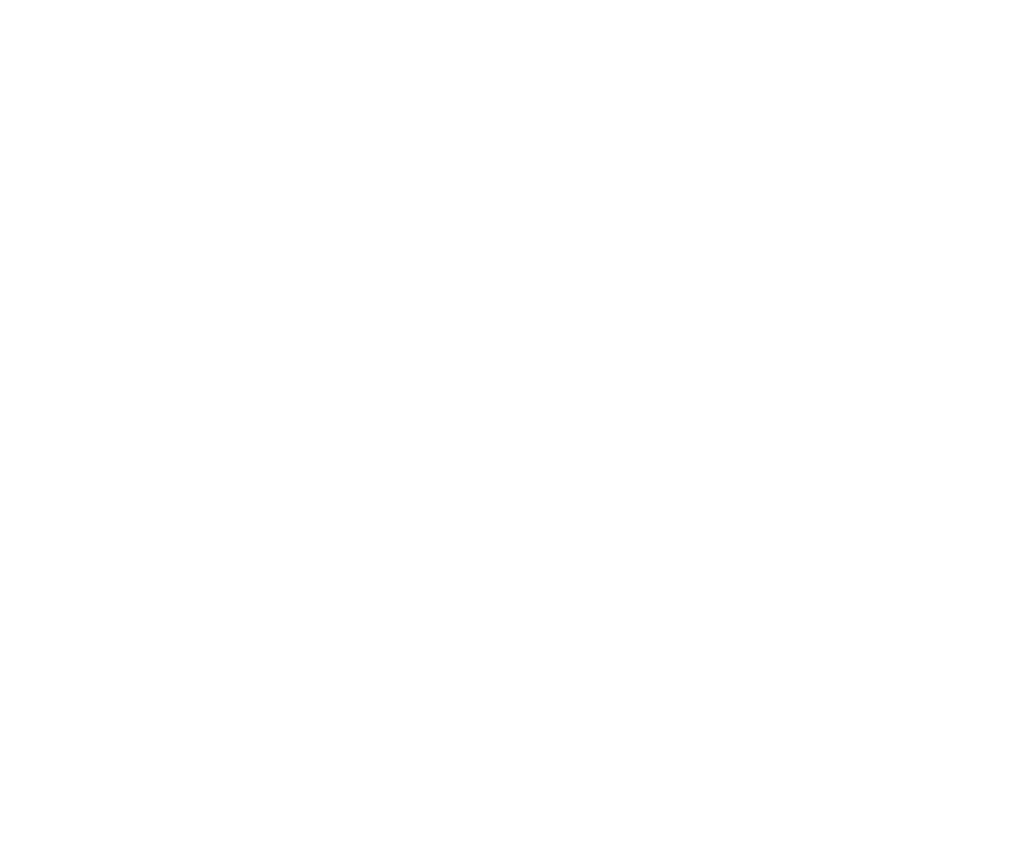 公式 X
公式 X