団員リレーエッセイ弁護士の声
おせっかいスキルを身につけた (後藤真紀子)
冬を迎えると、NICU(新生児集中治療室)に通った日々を思い出します。2ヶ月近くの早産で生まれた第二子は、生まれてから長期入院をしていたため、冬の間は毎日NICUに通っていたのでした。
医療事件を扱う弁護士として、産科の案件に遭遇することは少なくなく、2ヶ月早く生まれてくるということが相当にハイリスクであることは医師に言われなくても十分わかっていました。1週間近くの間、文字通り寝たきりで、眼鏡がないと全く見えない分娩監視装置を虚ろな目で眺めながら、装置から出るアラートに神経をとがらせる変な患者だったと思います。
なるべく早く出したい産科医と、胎児を極力胎内で成長させたい新生児科医の議論も垣間見え、それぞれの立場で最善の結論を出そうとしてくださっているのがよくわかりました。そうして生まれてきた我が子は、産科と新生児科との連携で、なんとか命を助けていただいたのですが、本来生まれるべき時期になっても退院はできず、長期入院をすることになりました。
第一子の時は必死だった新生児のお世話とは無縁で、保育器を眺めるだけの毎日でしたが、NICUの看護師さんたちは、厳しい状況の子どもたちがたくさんいるという雰囲気は全く出さずに、夜中の様子など、本当に細かく様子を教えてくださいました。臨床心理士さんも、NICU内を毎日のように回り、家にいる第一子のことも気にかけて話しかけてきてくださいました。
当然のことですが、医師は患者や家族に対して必ずしも良いことだけを伝えるわけではありません。厳しい内容であったり、現在の医学では説明できないことであったり、説明できないことであるのに何らかの決断を求められたり、多少の医学知識がある私でも、医師と話をする日は強い疲労を感じていました。
正直なところ、厳しい現実の中にいる患者やその家族は常に孤独にあって、他人から話しかけられること自体が煩わしく感じられることがあるのも事実です。しかし、思い返してみると、孤独の闇に吸い込まれていかずにいられたのは、たとえそれが煩わしく感じられたとしても、常に誰かが声をかけてくださったからだと思います。
このことを強く思い起こさせたのは昨年からのコロナ禍でした。私の身内の中にコロナ禍で手術を受けた者が2名おり、それぞれに家族としての対応が求められる機会がありました。入院中の家族に付き添うことはもちろんのこと、荷物すら直接届けられない中で、家族として説明を受ける時間も十分にはなく、お世話になっている看護師さんとのコミュニケーションもできない状況になり、短期で済んだから良かったものの、これがもう少し深刻な状況であったなら、患者本人のみならず家族も追い込まれることになるだろうと思いました。少し声をかけてくださる、ということの大きさを感じたものです。
自分の仕事を振り返ってみると、相談にいらっしゃる方は皆さん深い悩みの中にあり、必要なこと以外は話したくないような心境になっている方も多いと思うのです。私がまだ若手弁護士だった頃は、そういった方に対して、聞かれたくないことは聞かないでおいた方がよいのかな、と思っていた時期がありました。しかしそれは本当にその人のことを理解しようと思っての行動ではなかった。多少おせっかいで鬱陶しいと思われたとしても、「どうせ私のことはわからないでしょ」と思われたとしても、「私はあなたのことを気にかけています」「心配しています」というメッセージは、具体的な声かけをすることでしか伝わらないし、暗い闇を抜けた時に後からわかってもらえることもあるのだ、と思うようになりました。単に年をとっておせっかいになっただけなのかもしれませんが。
幸いなことに、第二子は、現在は定期的なフォローのみで元気すぎるくらいで、NICUにいらっしゃった看護師さんや臨床心理士さんと外来でお目にかかると、皆さん喜んで駆け寄ってきて成長を喜んでくださいます。きっと私が生まれた頃の時代であれば、助からなかった(諦められていた)に違いない子を全力で助けてくださった日本の産科救急と新生児医療の素晴らしさに改めて感謝し、日々奮闘されている医師、医療従事者の皆さんに深い敬意をもちながら、私も医療を良くするための活動として、医療事件に日々取り組んでいます。
以 上

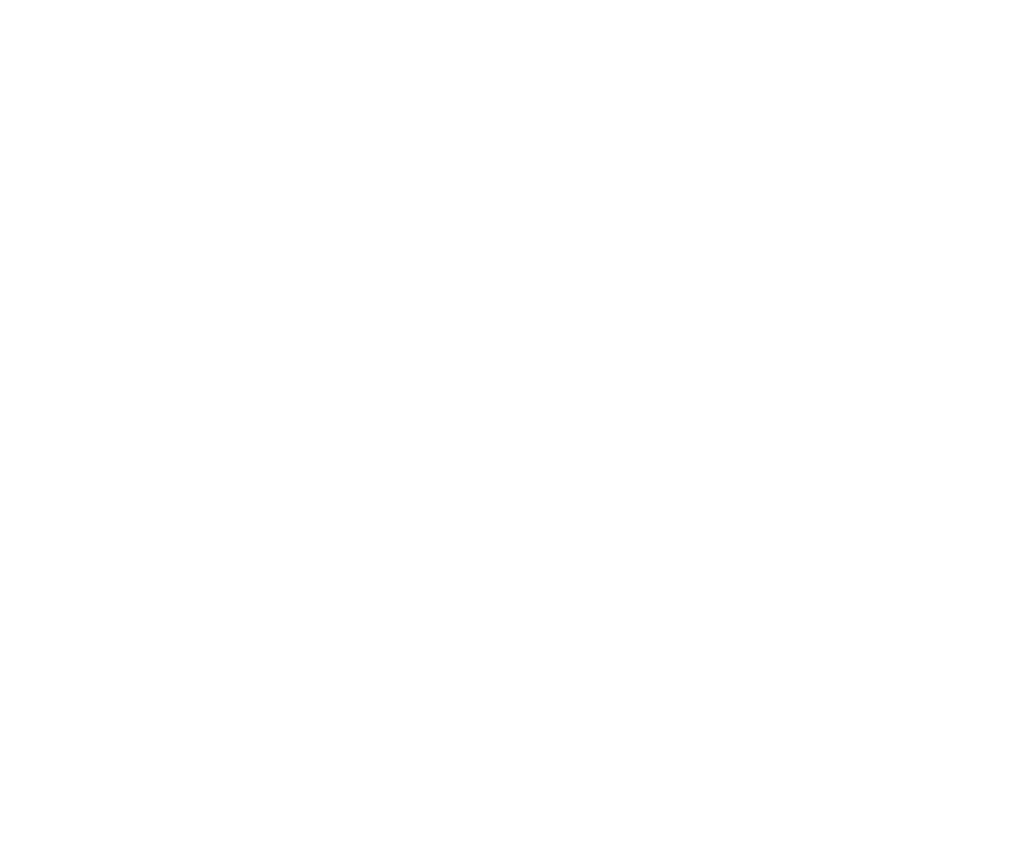 公式 X
公式 X