お知らせ(事件報告・提言)
医療事故と異状死体届出義務について
【要 約】
医療事故によって患者が死亡した場合も,医師は,異状死体等の届出義務を課した医師法21条の規定により速やかに所轄警察署への届出を行う義務があるとの意見を具申した。
「医療事故と異状死体届出義務について」
2001年12月20日
医療問題弁護団
代表 鈴木利廣
序.問題の所在
医師法21条に死体等検案医の異状死体届出義務が規定されている。
本条の規定違反が罰則の対象とされていることから、近年医療事故死についての届出義務の有無をめぐって、本条の解釈に意見の対立を生んでいる。
論点は次の2つである。
(1) 届出義務の対象である異状死体の概念ないし定義との関係で医療事故死は含まれるのか否か、含まれるとしてどの範囲かである。
(2) 届出義務の主体である死体等検案医の定義についてである。この関係では「検案」と「診断」の区別が問題とされている。
本稿の目的は医師法21条の解釈を明確にすることにあるが、合わせて医療事故報告制度のあり方についても述べることとする。
第1.異状死の定義
1 医師法21条、33条の規定内容
医師法21条は、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と規定して、医師に対し異状死体等の届出義務を課し、同法33条は、この義務に反した医師に対し、2万円以下(罰金等臨時措置法2条1項)の罰金刑を科している。
(※註 2004年10月現在上記医師法第33条は同法第33条の2に改正され、罰金額50万円と改められている。)
2 その歴史的経過と立法趣旨
(1) 歴史的経過
明治39年施行の旧医師法施行規則第9条に「医師死体または四月以上の死産児を検案し異状有りと認むるときは二十四時間以内に所轄警察官署に届出づべし」として、現在と同内容の規定ができ、その後、昭和17年制定の国民医療法の施行規則第31条にこの規定が移され、さらに同規則第65条で、違反者に50円以下の罰金または過料が科せられることとなった。
戦後、昭和23年の医師法制定の際、規則で定められていた上記規定が医師法の中に規定され、現在に至っている。
(2) 立法趣旨
この規定の趣旨は、死体には、犯罪が関連していることが多いため、死体に接しやすく専門的知識を有する医師に届出の義務を課し、犯罪捜査の端緒としようとしたものである。
すなわち、異状死体の届出がなされると、犯罪死の可能性がある場合には、検察官が犯罪との関連を調べるため死体を見分する「司法検視」が行われ(刑事訴訟法229条1項 これ自体は捜査ではない)、そこで犯罪性が認められれば、司法解剖等の捜査手続が開始される。
また、死体が犯罪とは明らかに関係がないと認められる場合には、警察官による「行政検視」の手続が行われ、さらに死因解明等の必要がある場合には、監察医制度のある地域では、監察医による検案、行政解剖(死体解剖保存法8条)が、監察医制度のない地域では、遺族の承諾が得られれば、一般医による行政解剖(承諾解剖 同法7条)が、それぞれ行われる。
また、このような当初の立法趣旨に加え、「社会生活の多様化・複雑化にともない、人権擁護、公衆衛生、衛生行政、社会保障、労災保険、生命保険、その他にかかわる問題が重要とされなければなら」ず、「異状死」の解釈もこれらの問題もふまえた上で広義に解釈すべきだとの日本法医学会「異状死」ガイドライン(平成6年5月)の指摘もある。
3 異状死とは
(1) 正常死と異状死
医師法21条が届出を義務づけているのは、医師が死体等を検案して「異状があると認めたとき」である。したがって、ここにいう「異状」の意味を明らかにしておかなければならない。
この点、純然たる病死、すなわち現に診療を受けているその病気により自然の経緯によって死亡したと確実に判断できる場合が「正常死」であり、この意味での純然たる病死以外の死はすべて「異状死」に含まれると解すべきである(「医学大辞典」南山堂 1998年、前掲日本法医学会「異常死」ガイドライン、高田利弘編「医科法律大辞典」医歯薬出版 1968年)。大審院大正7年9月21日判決は、旧医事法施行規則9条に関するものであるが、「異状」の意義について、「純然たる病死でない状況が死体に存する一切の場合を指称するのであって、医師が死因に犯罪の嫌疑がないと認める場合でも、その除外例をなすものでない。」と判示し、昭和9年に刊行された土井十二「医事法制学の理論と其実際」においても、「異常とは不自然な死を遂げ、その死因の不明な変死に限らず、明白なる病死の兆候が一切死体に存せない場合を云う」、「医師法規定の異常死体とは病死でない死を総称する」とされ、立法当初から、上記のような解釈がなされていたことが窺える。
なお、現医師法施行後の判例(東京地裁八王子支部判昭和44年3月27日)は「異状死」の意義につき、「右医師法にいう死体の異状とは単に死因についての病理学的な異状をいうのではなく死体に関する法医学的な異状と解すべきであり、したがって死体自体から認識できる何らかの異状な症状乃至痕跡が存する場合だけでなく、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況、身許、性別等諸般の事情を考慮して死体に関し異常を認めた場合を含むものといわねばならない。」と判示している。
(2) 医療事故死と異状死
(1)のような解釈にしたがえば、医療事故による死亡は、医療機関の過失の有無を問わず、純然たる病死といえないことが明らかであるから、医師法21条にいう「異状死」に該当し、当然に届出の対象となる。むろん、最終的に過失がないと判断されれば、医療従事者が刑事責任を問われることはない。ただ、過失の有無を判断し、訴追するか否かを決するのは検察官の職責なのであり、届出の際に医療従事者に過失など犯罪性の有無を判断させるのは妥当ではない。前掲大審院判決も、同様に考えるからこそ、医師が犯罪の嫌疑がないと認める場合でも届出義務の除外例とはならない旨判示しているのである。
(3) 日本法医学会ガイドライン
そして、前述の日本法医学会ガイドラインも、(1)のような解釈にしたがって、届け出るべき異状死の具体的ガイドラインを提示している。具体的には、以下のとおりである。
[4]診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
・注射・麻酔・手術・検査・分娩などあらゆる診療行為中、または診療行為の比較的直後における予期しない死亡
・診療行為自体が関与している可能性のある死亡
・診療行為中または比較的直後の急死で、死因が不明の場合
・診療行為の過誤や過失の有無を問わない。
[5]死因が明らかでない場合
・初診患者が、受診後ごく短期間で死因となる傷病が診断できないままに死亡した場合
・医療機関への受診歴があっても、その疾病により死亡したとは診断できない場合(最終診療後24時間以内の死亡であっても、診断されている疾病により死亡したとは診断できない場合)
(4) 四病協報告等の反論とこれに対する再反論
ア 四病協報告
ところが、この日本法医学会のガイドラインに対して、四病院団体協議会(四病協)医療安全対策委員会は報告をまとめ、「これでは予期されないあるいは診断が明確でないすべての場合が含まれてしまい、医療の実態に対応していない。医師法21条のごとく罰則規定のある条項の「異状死」を拡大解釈して、外因死や重大な過失による死亡を越えて、「ふつうの死」以外のすべてに適応することは、臨床的には適さない」と反論している。
しかし、国語的にも、「異状」とは「普通とはちがった状態」をいう(広辞苑第四版)のであるから、「ふつうの死」すなわち正常死について上記(1)のような解釈をとり、それ以外のすべての死を「異状死」とすることは何ら拡大解釈には当たらない。なお、「診断が明確でないすべての場合」というが、直接的な死因について明確な診断ができなくとも、現に診療を受けていた疾病による自然の経緯によって死亡したことが確実に診断できる場合には、「異状死」とはいえないのであるから、「異状死」の解釈が不当に広くなるということもない。
また、「臨床的には適さない」とするが、たとえ、「異状死」の範囲を広くとらえたとしても、それにより医師は所轄警察署に届出の義務を負うだけであり、しかも届出には特段の方式を要さず、口頭や電話で足るとされているのであるから、臨床医に対し特段の不都合を課すことにはならない。まして、これにより診療が萎縮化するということは到底考えられない。届出がなされても、死体に明らかに犯罪性が認められない場合は捜査手続は開始されず、臨床医が取り調べの対象となるなどの面倒を被ることもない。したがって、医師法21条による届出義務自体が、臨床医に不利益を課すものとは到底いえない。むしろ、特段の不利益がないにもかかわらず、届出の範囲を狭く解釈しようとする四病協の報告からは、医療機関の閉鎖的体質が窺えるといえる。
他方、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与えるという医師法21条の立法趣旨からすれば、死体についての犯罪性の有無の判断は、捜査機関にゆだねるべきであり、そのためには、あらかじめ届出の対象は広くしておくことが必要である。事故に関わった当事者である医師に犯罪性ないしは事件性の有無を判断させることは、事故の隠蔽にもつながり、医師法21条の立法趣旨にもそぐわない。特に、医療事故が多発し、しかも、都立広尾病院事件をはじめとして医療機関による事故の隠蔽行為が少なからず行われている現在の医療の実態からすれば、このことには特に留意しておかねばならない。
以上から、四病協の報告は適切ではない。
イ 日本外科学会等の声明文
また、日本外科学会等12学会(後に日本血管外科学会が加わり13学会)も、平成13年4月10日「診療に関連した「異状死」について」という声明文を発表している。この声明文は、「患者の取り違えや投薬ルートの誤り、異型輸血などの極めて初歩的な注意義務を怠った明らかな過失による医療過誤」については、医師法21条の届出義務があることを認めているものの、「(一定の割合で必ず危険を伴うという)外科手術の本質を考慮すれば、説明が十分になされた上で同意を得て行われた外科手術の結果として、予期された合併症に伴う患者死亡が発生した場合でも、これが刑事事件として違法性を疑われるような事件となるとは到底考えることは出来ない。」として、「臨床医の立場から、診療行為に関連した「異状死」とは、あくまで診療行為の合併症としては合理的な説明が出来ない「予期しない死亡、及びその疑いがあるもの」をいうのであり、診療行為の合併症として予期される死亡は「異状死」には含まれ」ず、医師法21条の届出の対象とはならない旨主張している。
しかし、2(2)で述べたとおり、医師法21条に基づく届出により直ちに刑事被疑事件として捜査の対象とされるわけではなく(この点で告訴・告発とは異なる)、捜査機関が犯罪死の疑いがあると考えてはじめて捜査手続が開始されるのである。そして、十分な説明に基づく同意がなされた上で行われた外科手術の結果、予期された合併症によってやむを得ず患者が死亡したことが明らかである場合に、なお犯罪の疑いがあるとして捜査手続が開始されるとは考えられず、これによって医師と遺族の信頼関係が破壊されるとか外科医が萎縮して危険性の高い手術を避けるなどということは到底考えられない(届出自体が臨床医の不利益にならないことは前述のとおりである。)。
また、上記声明文は、「過誤があったかどうかは、専門的な詳細な検討を行ってはじめて明らかになるものであり、まさに民事訴訟手続の過程において文献や鑑定の詳細な検討を経て判断されるのが相応しい事項である。」とする。しかし、同じことは、刑事上の過失の有無の判断についても妥当するはずである。そうであるならば、やはり、事故の当事者である医師に届出の要否を判断させるべきではなく、届出義務は広く課した上で、刑事責任の有無の判断は、捜査能力を有する捜査機関にゆだねることが必要となる。
さらに、診療行為の合併症として当然予期される死亡であっても、当該合併症が医師の過失によってもたらされた場合には、当然刑事責任追及の対象となりうるのであるから、診療行為の合併症として予期される死亡が当然に「異状死」に該当しないという理屈は成り立たない。
以上から、日本外科学会等の声明文も妥当ではない。
(5) 小括
医療の質を向上させるためには、医療事故の分野においても、刑事責任を問いうるものについては、適正に刑事手続が行われるべきである。そして、そのためには医療の透明性を確保し、死亡を伴う医療事故については、医療機関によって広く届出がなされることが必要である。そこで、医師法21条の「異状死」については、上記(1)のような解釈をとり、具体的には日本法医学会のガイドラインにしたがって、医療事故によって患者が死亡した場合、医師法21条の規定により速やかに所轄警察署への届出を行うことが、医師によって実践されなければならない。
第2.検案医の定義
1.「診断」と「検案」の定義
日本語の意味として、「診断」とは、生きている人を診察して、疾病の有無、疾病の内容を判断すること、「検案」とは、死んだ人を調べて、死因を医学的に判断すること、と考えるのが素直な読み方である。
このことは、そもそも、「診断」「検案」という文言が用いられて法律が作られた当時の解説、判例で、下記のアないしウのとおりの解釈(3.参照)がされていたことからも明かである。
ア 診断とは、生きている患者の病状を判断することであること
イ 検案とは、死んだ人の死体の状況を調べて確認することであること
ウ 人が死亡した場合には、その死体を検案して死因を確定するのが原則であること
2.定義をめぐる誤解
しかし、従来、医療界に存在してきた「診断」と「検案」の定義には誤解がある。
「診断」・「検案」と「死亡診断書」・「死体検案書」については、以下のような誤解がある。
医師法20条には、診断しないで診断書を書いてはならない(但し、受診後24時間以内に死亡した場合を除く)、検案しないで死体検案書を書いてはならないとある。
この規定を次のように誤解して、実務が行われている。
すなわち、
① 死亡診断書とは、医師が生前に診断すなわち診療行為を行った患者が死亡した場合に作成するものであるとの誤解。
② 死体検案書とは、その死体について一度も生前の診療を行っていない場合に作成するものであるとの誤解。
③ したがって、死体検案とは、生前に一度も診療を行っていない人の死体に関するものをいうとの誤解。
ここから、医師法21条にいう「死体を検案」とは、生前に一度も診療を行っていない死体を検案した時のことであるから、生前診療を行ったことのある患者が異状死した場合には届出義務はないと解釈するのである。この誤った解釈により、医療過誤で異状死した患者について、届出をしないことを正当化する口実にされている。
3.正しい定義の根拠
(1) 医師法20条の由来
診断、検案という文言が規定されているのは、医師法19条2項、20条、21条である。
これらのうち、19条は、旧医師法施行規則9条、20条は旧医師法5条、21条は旧医師法施行規則8条に由来している。
(2) 旧医師法時代の解釈
旧医師法は、昭和8年に一部改正された(前記①の各規定内容は変わらず)が、その当時、刊行されていた解説書において、池松重行、衛生局事務官池田清士、医学博士・法学士土井十二は、
診療とは、生きている患者について一定の行為を行うこと、
診断とは、生きている患者について医学的に判断すること、
検案とは、死んだ人を調べて死因について判断すること
との定義を前提として論述している。
① まず、池田清士(法学士・衛生局医務課事務官)の解説(「改正医師歯科医師法令釈義」昭和8年11月発行)によると、
「検案とは死體又は死胎に対し一定の者(医師及び産婆)が其の主観に基づきて為す専門的判定である。」としている。
② 土井十二(法学士、医学博士)は、次のように解説している(前掲「医事法制学の理論と其実際」昭和9年3月刊)。
「死亡診断書とは、従来診療する患者が死亡した際、その生前における診察に基づき、死亡の原因を医学的に証明するための文書である。本来死亡診断書の作成に当たって、死体を検案して、死因を確定するのが原則ではあるが、診療中の患者が、その疾病のために死亡せるものと推定する場合には、再度死体を「検案せずして」直ちに、死因を証明する死亡証書を交付することを、「診療中の患者死亡したる場合に交付する死亡診断書についてはこの限りにあらず」によって認めて居るのである。」
③ 池松重行「改正医事法制論」(昭和9年4月発行)は、次のとおり述べている。
「死亡診断書とは診療中の患者死亡した場合に、その死因を証明するために医師の作成する文書である。死亡診断書は患者の死因を確認するものである以上、これを作成するためには親しく死体を検案するが原則であるも、患者の生前よりすでに診療をなし、これにより死因を判断しうべき状況にある時は、新たにその死体を検案せずして死亡診断書を作成することを得る。即ち、医師法(注・旧医師法)5条に『但し診療中の患者死亡したる場合に交付する死亡診断書についてはこの限りにあらず』と規定す。」
(3) 判例
下級審判例として前掲東京地裁八王子支部判昭和44年3月27日がある。この判決では、入院中の患者が死亡前約2日間病院を脱走して所在不明となって、死体となって発見された患者について、診療していた医師が死体を調べて死因を判断した行為を「検案」と表現している。
4.死亡診断書と死体検案書の関係
(1) 死亡診断書・死体検案書の法的意義
生前に診療中の患者であってもそうでなくても、医師が死体を調べることが「検案」にあたることは、以上述べたとおりである。
そして、検案の結果を記載するものが死体検案書である。
ただ、その死体が死亡前24時間以内に受診した診療中の患者であり、生前診断していた疾病により死亡したものであることが明らかな場合には、例外的に死体を検案しないで生前の診断に基づいて「死亡診断書」を作成できるとした(この場合は死後の検案に基づくものではないので「死体検案書」とすることはできない)。これ以外の場合に死亡診断書を作成・交付する法的根拠はない。
つまり、死体を調べて死亡と死因を確認した医師が作成するものはすべて「死体検案書」であり、本来法律上に規定されている。「死亡診断書」とは、死体を見ないで生前の診断に基づいて死因を証明する文書なのである。
(2) 現行医師法20条但書
旧医師法5条は、死亡前に医師により診療が行われていた患者について、診療していた疾病で死亡したと推定される場合には、改めて患者の死体を検案するまでもないということで、例外的に、生きていた時の診断に従って作成した死亡診断書を交付してよいという趣旨である。
現行医師法20条は、旧医師法5条から国民医療法10条に引きつがれたものが、さらに引き継がれたものである。ただ、検案しないで作成できる死亡診断書を交付できる場合については、但書で、「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」と、時間的な制限が設けられた。
この規定は、旧医師法、国民医療法の規定では、生前の診断から予期された死因であることが明らかであれば、死亡した時期を限らず死体を一切検案しないで作成する死亡診断書を交付することができることになっていたものを、時間的に受診後24時間以内の死亡に限定したものである。受診後24時間以後である場合には、但書に定めた例外には該当せず、あらためて検案をした上で生前診断していた疾病により死亡したことを確認する必要がある。この場合に作成するのは原則どおり死体検案書になる。
(3) 厚生労働省の死亡診断書記入マニュアル
厚生労働省は、死亡診断書記入マニュアルを発行しているが、その平成13年度版には、死亡診断書と死体検案書のいずれを書くべきかについて、フローチャートが載せられている(その流れは、後述のとおり当意見からすると正しくないが)。その中で、「死亡の原因は、診療にかかる疾病と関連したものですか?」の問いに対して、はい、いいえで分かれ、その後に「死体を検案して異状があると認められますか。」との問いがなされているのは、診療継続中であった患者の場合でも、死体を調べることが「検案」にあたることを当然の前提としているからである。
以上述べてきた当見解から、同マニュアルのフローチャートは、次のように訂正される必要がある。
死亡診断書と死体検案書の使い分け
死体を検案しましたか。
は い→☆死体を検案して異状があると認められますか。
は い→24時間以内に所轄警察署に届け出ます。
→医師(監察医等)が死体検案書を発行します。
いいえ→交付の求めに応じて死体検案書を作成します。
いいえ→死亡者は診療継続中であった患者ですか。
は い→受診後24時間以内に死亡した患者ですか。
は い→診療にかかる疾病によることが明らかな死亡ですか。
は い→交付の求めに応じて死亡診断書を作成します。
いいえ→求めがあれば死体を検案したうえで☆へ
いいえ→求めがあれば死体を検案したうえで☆へ
いいえ→求めがあれば死体を検案したうえで☆へ
なお、かかる死亡診断書は、死体検案なしに作成するものであるが、現代的意義は乏しい。すなわち、死体検案が不可能な場合はともかく、可能であれば検案後に死体検案書を作成することが望ましい。
(4) 昭和24年4月14日医発385号について
厚生省医務局長通知に次のようなものがある。
医師法第20条但書に関する件
(昭和24年4月14日医発第385号各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知)
標記の件に関し若干誤解の向きもあるようであるが、左記の通り解すべきものであるので、御諒承の上貴管内の医師に対し周知徹底方特に御配意願いたい。
記
1 死亡診断書は、診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、苟もその患者が診療中の患者であった場合は、死亡の際に立ち会っていなかった場合でもこれを交付することができる。但し、この場合においては法第20条の本文の規定により、原則として死亡後改めて診察をしなければならない。
法第20条但書は、右の原則に対する例外として、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に限り、改めて死後診断しなくても死亡診断書を交付しうることを認めたものである。
2 診療中の患者であっても、それが他の全然別個の原因例えば交通事故等により死亡した場合は、死体検案書を交付すべきである。
3 死体検案書は、診療中の患者以外の者が死亡した場合に、死後その死体を検案して交付されるものである。
この通達は、「死亡診断書は診療中の患者が死亡した場合に交付されるものである」とか、診療中の患者が死亡した場合においては「原則として死亡後改めて診察をしなければならない。」、「改めて死後診断をしなくても」など、誤った解釈や表現があり、誤解を招く。
「死亡診断書」については、「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合で、死体を検案しなくても死因を診療中の疾病の診断に基づいて判断できるものについて交付されるものである」とし、それ以外は死体検案して死体検案書を作成すべきである。
第1項但書の、「原則として死亡後改めて診察をしなければならない。」は、「原則として死亡後改めて検案をしなければならない。」とすべきである。
また、「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に限り、改めて死後診断しなくても死亡診断書を交付することを認めた」とあるが、「死後診断しなくても」ではなく、「検案しなくても」が正しい。
5.まとめ
以上から、医師法21条にいう「死体を検案」するとは、生前に診療中の患者でもそれ以外の患者でも、すべて死体について医学的に調べて死因を確認することなのであり、診療してきた患者が死亡して、主治医が確認することも「検案」にあたると解釈すべきなのである。
従って、医師法21条の規定する検案医は、生前に診療を行っていた患者を検案して異状死と確認したものを含む。
第3.医療事故のあるべき報告制度について
1.現状の報告制度
医療事故について報告制度の必要性は論をまたない。何よりも事故例について徹底した原因の調査・分析を行い、再発防止や被害救済に資することが求められている。
医療事故についての医療機関からの報告制度といえるものは、
① 各医療機関の外部への任意報告システム(注1)
② 医師法21条に基づく異状死届出義務
③ 刑事訴訟法239条2項に基づく公務員の犯罪告発義務
④ 医薬品の副作用・医療用具の不具合についての企業(薬事法77条の3、2項に基づく協力)及び厚生労働省(平成9年5月15日付局長通知に基づく協力)に対する報告
⑤ 損害賠償責任保険契約に基づく保険会社への報告
がある。
そこで、上記システムが、再発防止や被害救済につながっているかが問題となる。
上記①は、報告については当該組織の自発的行動に期待する他ないばかりか、必ずしも報告をうけた機関が再発防止や被害救済につなげるとは限らない。
②③については、前述したごとく、制度目的たる犯罪の覚知機能からすれば、個人の法的責任の確定や社会的警告の意味はあっても、再発防止や被害者救済に直接的に資する制度としては不充分である。
④については、企業及び厚労省による再発防止のための警告、出荷停止、回収につながる可能性を有しているが、その活動の実情について不充分であるとの指摘もある。
⑤については、被害者救済につながりうる可能性はあるが、再発防止としては無力である。
2.あるべき報告制度
前述した医療事故報告制度の目的や現状の不備を前提とすると、あらゆる医療事故例について一元的に報告をうけて、調査・分析を行い、再発防止措置及び被害救済につなげてゆく機構が必要不可欠である。
そして、その報告義務者として、医療機関のみならず、医療産業(医薬品、医療用具)、損保会社等のすべての医療事故情報保有者を想定すべきといえる。また、被害者(患者、家族)からの報告も受け付けるしくみが必要である。
かかる報告制度案としては、日本弁護士連合会の提言(「医療事故被害者の人権と救済」明石書店 2001年)、加藤良夫氏の「医療被害防止・救済センター構想」(2001年8月)、患者の権利法をつくる会(本部 福岡市)の「医療被害防止・補償法要綱案骨子」(2001年9月30日)が大いに参考となる。
3.医療事故報告制度と刑事免責について
医療過誤を起こした医療者やその医療機関に対し事故報告義務を課しても、刑事処分(業務上過失致死傷罪)のおそれがあると報告の実があがらないので、自発的報告を促進することを理由に、報告をした事案については刑事免責を与えるべきであるとの意見がある。現に米国において一部の州で実施しているともいわれている。
しかし、こうした政策は正しいのであろうか。
まずもって市民の賛同が得られにくい政策である。
今まで膨大な数の医療過誤症例が医療機関によって隠されてきたことは想像にかたくない。近年その一部がマスメディアによって明らかにされたこともあって、自発的に公表する医療機関が登場しはじめたのも事実である。過誤隠しは過誤自体より社会的批判性が高いとの風潮もあって隠しにくくなってきていることも一因である。
医療事故の自発的報告に刑事免責を与えなければならない政策的根拠は、事故の実情を把握するには、自発的報告に頼らなければならないと考えるからであろう。自発的報告に頼らざるを得ない土壌には、医療者間のかばい合いや医療の閉鎖性ゆえに事故・過誤隠しが容易であることがあげられる。
重要なのは患者や社会に対する情報開示と説明責任を医療倫理として確立し、患者の人権の視点に立った医療の透明性を高めてゆくことであり、そうすることによって医療事故の報告制度は実効性をあげることができると考える。
なお、交通事故では、車両の運転者に刑事免責なしに報告を義務づけている(道交法72条1項後段)ばかりか、報告義務違反に罰則を課している(同法119条1項10号)。医療事故に刑事免責を与えるべき合理的理由は今のところ見出しがたい。
注1
(1)厚生省「リスクマネージメントマニュアル作成指針」
(H12.8 国立病院における指針)
過誤による死亡及び傷害について警察へ「届出」を行うとしている
(2)大阪府「医療事故防止対策ガイドライン」
(H12.9 大阪府立病院における指針)
異状死「届出」義務の他に保健所等関係行政機関への「報告」をするとし ている
(3)都立病院医療事故予防対策推進委員会「医療事故マニュアル」
(H12.11 東京都立病院における指針)
医療事故死については日本法医学会「異状死」ガイドラインを参考とする としている他、過失による死亡及び重篤な傷害について警察に「届出」を行 うとしている
(4)国立大学医学部附属病院長会議作業部会提言
(H13.3 国立大学病院における指針)
医師法21条の法的解釈論は別との前提で、刑事罰対象事故については警 察に「報告」し、都道府県の医療担当部局へも「報告」するとしている
参照条文
旧医師法(明治39年施行)
第5条 医師は自ら診察せずして診断書、処方箋を交付し若しくは治療をなし、または検案せずして検案書若しくは死産証書を交付するを得ず。但し、診療中の患者死亡したる場合に交付する死亡診断書についてはこの限りにあらず。」
旧医師法施行規則
第8条 医師死体又は4ヶ月以上の死産児を検案し異常ありと認むるときは24時間以内に所轄警察官署に届出づべし。
第9条 医師は法令の規定により必要あるものに正当の事由なくして診断書、検案書又は死産証書の交付を拒むことを得ず。」
国民医療法(昭和17年)
第9条 診療に従事する医師又は歯科医師は診察治療のもとめある場合において正当の事由なくしてこれを拒むことを得ず。
診察又は検案をなしたる医師は診断書、検案書又は死産証書の交付のもとめある場合において正当の事由なくしてこれを拒むことを得ず。
第10条 医師は自ら診察せずして治療をなし、診断書若しくは処方箋を交付し又は自ら検案せずして検案書若しくは死産証書を交付することを得ず。但し診療中の患者死亡したる場合に交付する死亡診断書についてはこの限りにあらず
国民医療法施行規則
第31条 医師死体又は4ヶ月以上の死産児を検案し、異状ありと認むるときは24時間以内に所轄警察署に届出ずべし。
第65条 第31条の規定に違反したるものは50圓以下の罰金又は科料に処す。
医師法(昭和23年)
第19条 ② 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求めがあった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めた時は、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

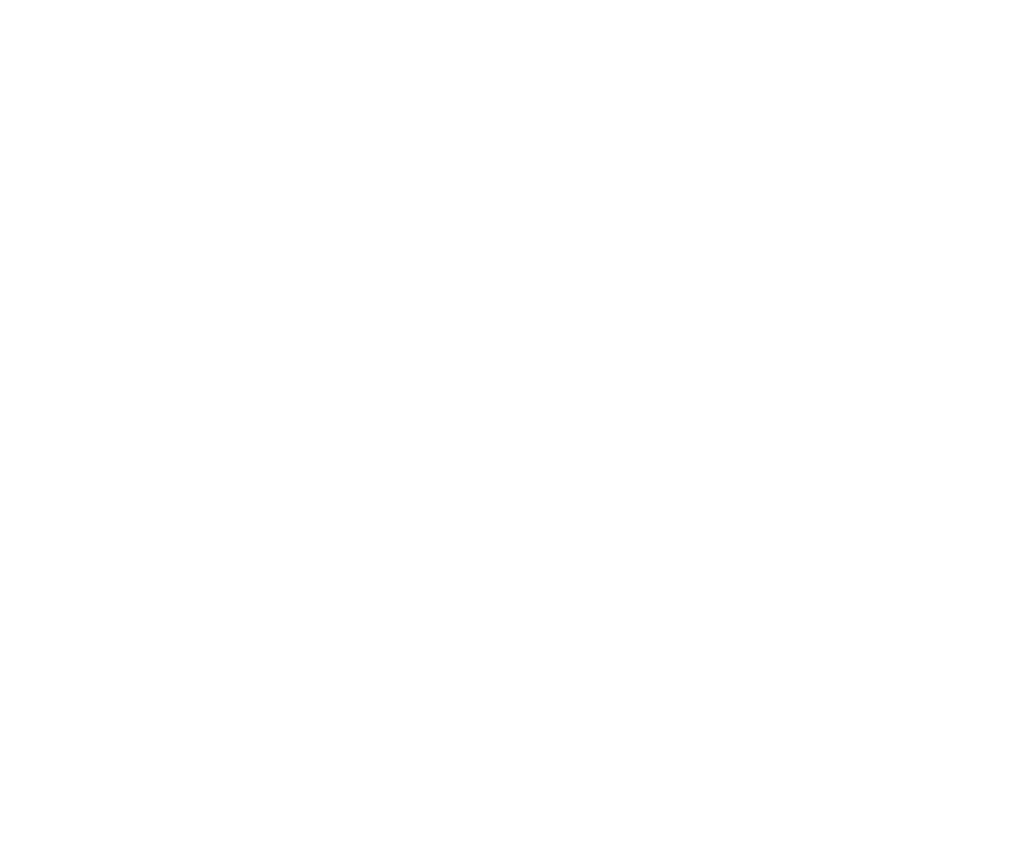 公式ツイッター
公式ツイッター