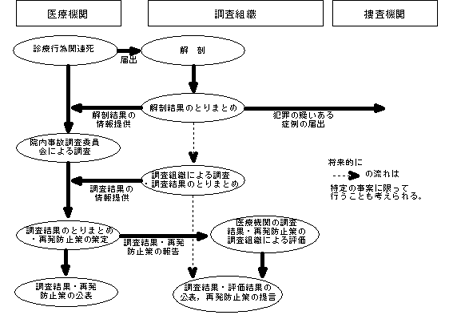当弁護団は、東京を中心とする250名余の弁護士を団員に擁し、医療事故被害者の救済、医療事故の再発防止のための諸活動等を行い、それを通じて、患者の権利を確立し、かつ、安全で良質な医療を実現することを目的とする団体です。
標記第三次試案に関して、下記のとおり、意見を提出いたします。
医療問題弁護団
代表 弁護士 鈴 木 利 廣
はじめに~第三次試案についての総括的評価第三次試案は、医療事故防止の視点からみて、細部に多少の問題点はあるものの、現時点において医療界の理解を得られるべく最大限努力した試案と考える。医療事故調査のあり方が社会問題化した1999年からの、いわゆる医療事故危機からすでに10年目を迎えたいま、医療事故調査システムの確立は急務である。厚労省に求められるのは、可能な限り迅速に法案作成のうえ、国会審議に付すべきことである。
第1.医療機関の法的責任との関係
1.届出義務違反に対する対応 ~(21)(22)に対して届出範囲か否かの判断は、「明らか」「起因」「予期」との評価的判断を含むものであり、しかも医療機関の主観的判断を尊重し、かつ故意の届出違反、虚偽届出及び体制不備による不届出に限って行政命令だけがなされる仕組みである。重要なことは届出が促進され、“正直者が馬鹿をみる”という公平性を損なうような取扱にならないようにすることである。届出促進のための啓発研修や行政命令違反へのペナルティーも検討すべきである。*(21)図表
医療安全調査委員会(仮称)へ届け出るべき事例は、以下の①又は②のいずれかに該当すると、医療機関において判断した場合。
(①及び②に該当しないと医療機関において判断した場合には、届出は要しない。)*(22)届出範囲に該当すると医療機関の管理者が判断したにもかかわらず故意に届出を怠った場合又は虚偽の届出を行った場合や、管理者に報告が行われなかった等の医療機関内の体制に不備があったために届出が行われなかった場合には、医療機関の管理者に、まずは届け出るべき事例が適切に届けられる体制を整備すること等を命令する行政処分を科すこととする。
このように、届出義務違反については、医師法第21条のように直接刑事罰が適用される仕組みではない。
2.刑事責任(業務上過失致死罪)との関係
~(39)(41)(別紙3、問い4答1)に対して地方委員会が捜査機関に通知を行う事例については、故意・重大な過失等に限定することとされている。そして重大な過失とは、「医療専門家による・・・医学的な判断」として「標準的な医療行為から著しく逸脱した医療」とされている。このことが記述にかかわらず、地方委員会が法的判断を行うかのように誤解されうる。そこで、医療界の誤解を避けるためには、「故意・重大な過失」という法的責任・法的判断と誤解されやすい用語の使用を避ける必要がある。*(39)医療事故による死亡の中にも、故意や重大な過失を原因とするものであり、刑事責任を問われるべき事例が含まれることは否定できない。医療機関に対して医療死亡事故の届出を義務付け、届出があった場合には医師法第21条の届出を不要とすることを踏まえ、地方委員会が届出を受けた事例の中にこのような事例を認めた場合については、捜査機関に適時適切に通知を行うこととすることが、医療事故の特性にかんがみ、故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例に限定する。*(40)診療行為そのものがリスクを内在するものであること、また、医療事故は個人の過ちのみではなくシステムエラーに起因するものが多いこと等を踏まえると、地方委員会から捜査機関に通知を行う事例は、以下のような悪質な事例に限定される。
(1)医療事故が起きた後に診療録等を改ざん、隠蔽するなどの場合
(2)過失による医療事故を繰り返しているなどの場合(いわゆるリピーター医師など)
(3)故意や重大な過失があった場合(なお、ここでいう「重大な過失」とは、死亡という結果の重大性に着目したものではなく、標準的な医療行為から著しく逸脱した医療であると、地方委員会が認めるものをいう。また、この判断は、あくまで医療の専門家を中心とした地方委員会による医学的な判断であり、法的評価を行うものではない。)*(別紙3、問4答1)委員会の調査報告書については、公表されるものであるため、委員会から捜査機関に通知を行った事例において、捜査機関が調査報告書を使用することを妨げることはできない。
第2.医療安全調査の質の確保をめざして厚労省試案及び検討会議論は、いわば医療事故調査の枠組論である。どんなに立派な器ができても、肝心の調査の質が低ければ、再発防止目的は達せられない。臨床医中心の調査が医療の質の向上をめざす優れたピアレビュー(同僚審査)になるのか、医療の不確実性を過度に強調して医療現場をかばい合う結果になってしまうのか問われている。
ここでは、調査の質の確保という観点から、第三次試案に潜む問題点について言及する。
1.裁判手続と原因究明 ~(3)に対して裁判手続による証拠調やこれに基づく判決が原因の究明につながらないとの論調は司法制度や法曹の判断を軽視するものであり、調査活動への法律家参加に少なからず悪影響を及ぼしかねない。なお、司法手続きによっても原因究明につながらないものがあること及び司法手続による原因究明が直ちに再発防止につながらないことは、司法の限界として認識しておくべきことと考える。*(3)死因の調査や臨床経過の分析・評価等については、これまで行政における対応が必ずしも十分ではなく、結果として民事手続や刑事手続にその解決が期待されている現状にあるが、これらは必ずしも原因の究明につながるものではない。
2.医療事故調査の担い手と役割 ~(10)(31)に対して医療事故調査は解剖担当、臨床評価担当の医療関係者と法律家、有識者によって構成されるが、それぞれの役割をモデル事業における評価の実践等を踏まえ、指針等に明示することが重要と考える。*(10)調査チームのメンバーは、臨床医を中心として構成し、具体的には、日本内科学会が関連学会と協力して実施中の「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」(以下「モデル事業」という。)の解剖担当医2名、臨床医等5~6名、法律家やその他の有識者1~2名*(31)全国均一に、かつ、継続して適切な評価を行うため、評価の視点や基準についての指針等を作成するとともに、解剖担当医や臨床評価担当医等に対する研修を実施する。
3.診療経過の調査 ~(27)(34)に対して事故調査は過去の歴史的事実の再現である。診療経過事実の調査に際しては、診療記録や関係者の記憶に再現性が低いこともあってしばしば患者側と医療関係者の認識が対立する。今後、術中ビデオの義務化や診療記録記載指針の作成等を通じて再現性の高い診療経過を残すことに努力すべきと考える。*(27)個別事例の調査は、原則として、遺族の同意を得て解剖が行える事例について以下の手順で地方委員会の下に置かれる調査チームが行う。①~⑦は略。*(34)院内において調査・整理された事例の概要や臨床経過一覧表等の事実関係記録については、地方委員会が診療録等との整合性を検証した上で、地方委員会での審議の材料とする。
4.医療事故の2つの類型 ~(29)に対して医療事故には医原病型(侵襲性のある医療行為を原因とする合併症、副損傷、副作用等)と疾病悪化型(治療の不実施や遅れによる疾病の悪化)の2つのタイプがある。「疾病自体の経過としての死亡」であっても、診断治療の遅れが問題となりうるのであり、医療事故防止の観点から「調査は継続しない」とすべきではない。*(29)医療機関からの届出又は遺族からの調査依頼を受け付けた後、疾病自体の経過としての死亡であることが明らかとなった事例等については、地方委員会による調査は継続しない。(この場合には、医療機関における説明・調査など、原則として医療機関と遺族の当事者間の対応に委ねることとする。)以上

 公式 X
公式 X